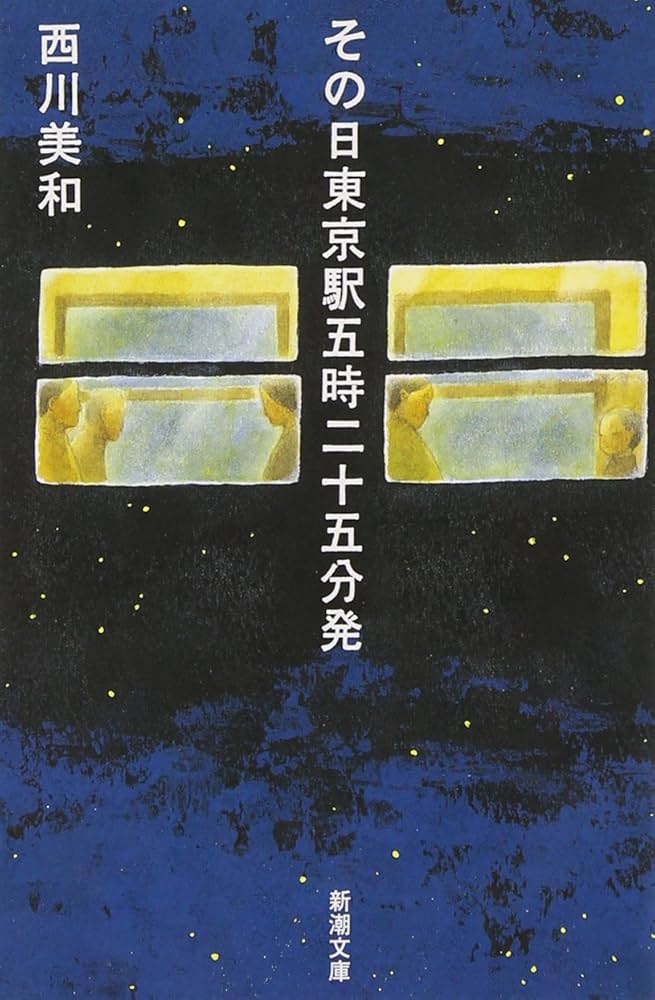千葉の郊外から東京の学校に通っていた日々、満員電車の路線図を眺めながらよく想像していたことがある。
まるでその中心に通い詰める路線の数々は、体内に張り巡らされた動脈のようだと。
血液として酸素と栄養素を搾り取られ、疲れ果てた我々は、やがて静脈に流されて帰路に着く。東京に集中された路線図は、その血液を集中された巨大な脳みそそのものなのだと。
あるいはそこで知識や経験や給料を得て、それぞれの地に栄養と酸素を運び戻す心臓の如くでもあったのかもしれない。
いずれにしてもその路線図は、そこに乗り運ばれる私たちの個性を剥ぎ取って、集団性の中で形作られた巨大な存在に生命を捧げるように迫る、現代社会における血の祭壇かのように映ったのだ。
まあ青年によくありがちな厭世観ではあったのだが。
しかしいざ東京そのものに暮らし始めた日々、千葉の郊外に比べて東京に特別なところはなかった。
むしろ建物は狭ぜまとして窮屈に敷き詰められ、住宅もまた同じ。凄まじい土地の価格に呼応するように無駄なく何かしらが敷き詰められていた。
古いもの、効率性の失われたもの、人々の注目を失ったものは容赦なく打ち壊され、新しいものに建て替えられていった。家もまた古い日本家屋は壊されては細かい分譲になった。
そんな土壌で古より受け継がれてきたような土着的なもの、生の息吹に満ちた古い地霊は、いたずらに跳ね上がる土地の価格の下に窒息していた。
しかし利便性に敷き詰められるアスファルトとコンクリートの世界だからこそ、その中に保たれた広さ、古さの豪奢は余計に人の目を引くものである。
特に東京の都心の中で広さ、古さを保ち得るもの、それこそ日本の頭脳であり、心臓であった。
その一つでもある大学に通っていた私が東京に住むことを渇望したのは、中身を運び、吸われ、また中身を得ては運び疲れる日々に、己が主体性を取り戻したかったからかもしれない。
遠方から東京に通わなくても良い人間、その頭脳、心臓の一部として地に一体化することで、己が自我を取り戻せるような気がしていたのだろうか。
まるで近所の公園のように、卒業した大学の図書館に足を運んだ日々、若さに躍る学生と外部の人間たちから結界を張られた静寂の世界、それはかつての貴族や王、そして現代のごく一部の特権を持った者たちにしか味わい得ない、世に秘められた甘み、軽みを与えてくれたものだった。
しかし東京に通う悲しさは、もともと地元で得られていた生が、東京という社会的求心力に奪われる大人の悲しみでもあった。子供らしい喜び、人間の当たり前の生は、東京でなくても得られるというのに。
当たり前の恵みから引き離され、孤立した個人として主体性をもち、通勤通学の者たちを憐んでいたつもりでいて、彼らが帰るべき地の豊穣を忘れていただけなのかもしれない。
それが東京を模した灰色の郊外だったとしても、常軌を逸した価値を付されていないその土地の間からは、何かしら人間的な文化が芽吹いていた。
しかしいざまたこの東京から離れるとなると、一抹の寂しさを覚えるものである。
大学図書館や国会図書館の静けさに思考を透かし、北の丸公園にひっそりと繁る森を抜け、人気のない丘から千代田の均整の取れた街波を眺め、上野の文化財に親しみ、池袋や渋谷のお祭り騒ぎのごとき雑踏に混じる。
新宿の小さな映画館や神保町の片隅で憧れの知性と出会い、時に名声ある人々と隣り合う。
日本中から人を惹き集めた上で築かれ、保たれた文化から距離を置かねばならぬのは、やはり寂しい。
しかし幼子は広さを求め、繋がりを求め、自然の中での呼吸を求める。いかなる東京の喜びも誇りも、純朴たる生の喜びを失った大人の足掻きであり、子供たちと共に分かち合うには10年の時を待たなければならない。
それにだ、もし東京の刺激が懐かしいのなら、スマホでも見とけばあっという間に付くよね。今どきは。