コイナーさんについて
コイナーさんは客としてもてなされるとき、あてがわれた部屋は最初の状態のままにしておいた。
個人がその環境に自分のしるしを押すのは、つまらないことだと思っていたからだ。
逆にコイナーさんは、自分の存在を、泊めてもらう部屋に合うように変えようと努力した。
だからといって、これこそが彼の狙いだったのだが、居心地が悪くなることは許さなかった。
どんな環境でも、夢のように自分にぴったりの環境なんて存在しないだろう。学校でも職場でもなんでも、自分を喜ばす存在も当然あるけれど、自分に合わないもの、苦手なもの、苦痛を強いるものもまた、少なくはないのではないだろうか。
そんな環境とは時に戦い、葛藤するのも大いに善いことだろう。しかしコイナーさんのように、部屋の環境に自分を合わせたって別に良いのだと思う。
ほとんどブレヒト本人の化身であるコイナーさんが、彼の豊かな感受性を宿して居心地よく部屋にいるのであれば、たとえそこが不正や苦悩に満ちた部屋であったとしても、美しい詩の1つや2つ、心の中に湧いて出てくることもあるだろう。
部屋の環境に「我」を押し付けて部屋の環境に印を残すのは素晴らしいことだ。とはいっても、部屋と自分との相違など気にしないで、「我」に安らぎと喜びを与えるのだって、おんなじぐらい素晴らしいことだと思う。「居心地の良さ」が、いつか花を咲かせることもあるだろう。
そんなコイナーさんだから、下のような話もしてくれたのだろう。
よその家に行って泊めてもらうとき、コイナーさんは休む前に、必ずその家の出口の数だけはチェックした。
理由を尋ねられて、きまり悪そうに答えた。
「昔からの困った癖でしてね。バランスが気になるんです。自分が入った家に出口が1つ以上あると、安心できるので」
ー同上、「コイナーさんの物語」より
誰が1つの部屋に留まっていなければならないと決めたのだろうか。部屋に合わせるべく努力しても居心地が悪いなら、そんな部屋など出て行ってしまっても構わないのではないだろうか。
それは単にコイナーさんの悪癖で、たとえ出口を知っていたにしても、本当に出ていくことは滅多にないのかもしれないのだけれど。
模様替えの怪
都内での引越しが多い。家賃が高いから、その五千円から一万円の間に凝縮されている細々とした条件を吟味しなければならない。
何よりも広さ、木造が鉄筋コンクリートか、窓はいくつあるか、駅までの距離、周囲の景色、図書館やスーパーの有無といった絶対条件が、数千円の違いによって激変する。
ひいては台所は広いか、水周りが妙に昭和じみて哀愁を誘わないか、幽霊は出るか、隣人がモンスターか否かといった、無限にも等しい条件を鑑みる。
しかし良い物件はすぐ埋まる。それに少しでも欲をかけば値段が激増するから、自然に選択肢は狭まり、あとは運次第。不動産屋さんの機嫌を損ねないように気を使いつつ、色々とわがままを言っているうちに成り行きでさらっと決まってしまう。
気分やタイミング、内覧時の天候、あるいは不動産屋に叩いた軽口の一つで、部屋との出会いの運命は大きく左右されているはずである。なのに半年ぐらい住んでみるといつも、その部屋以外の選択はあり得なかったように思うのが不思議だ。そのなり行きの選択に、どれほど細やかな必然が伴っていたかに驚くのである。
個人的な趣向で、玄関のドアを開けた瞬間にわっと空間が広がる部屋が好きである。天井が高くて、部屋の隅々までを見渡せる空間。それは時に正方形に開けた間切りのない1DKであったり、横長に広がりを見せる2DKだったりする。
そんな空間のどこかに、まず大きな机を置く。座り心地の良い椅子も置く。書斎の完成である。そして最近買ってしまったばかりの、まるでどこぞの予備校にでもおかれるような巨大なホワイトボードも置く。強力なマグネットで絵画のポスターを貼ったリ、混沌とした思考を書き出して整理したり、目標や早急の課題を書き出すのだ。書斎が華やぐ。
次にベットを置く。ベットの上か横に、植物と目覚まし時計をおき、寝室の完成。そしてここで、いつもお決まりの悩みのたねに出くわす。
冷蔵庫をどこに置くべきか。
こんなにも巨大で常に電力を求める存在でありながら、台所の周囲に置き所は限定されている。台所と言っても、私の借りる部屋に台所とリビングの間切などない。この冷蔵庫をどこに置くかによって、私の生活環境は激変するのである。
まるで結界を有するかのように、冷蔵庫の置かれた周囲数メートルは、たちまち台所スペースとなる。そこはものを買い込み、煮炊き、食い、消化する場所である。それ以外に何をしようもない。
しかし欲を言えば本棚も置きたいし、映画鑑賞スペースも欲しい。寝室に近すぎると冷蔵音は夜の静寂をかき乱す。うるさいから遠くにいてもらいたい。
この三代環境。書斎、寝室、台所が、都内の狭い賃貸空間の中で、毎度熾烈なせめぎ合いを織り成すのだ。
台所の支配を極力小範囲に抑え、書斎の拡大を試みる。しかし台所を狭くしすぎるとたちまち自炊の気力は萎え果て、食費が高騰するか栄養状態が低下する。寝室をむげにすれば結果は明白だろう。睡眠ほど重要なものはない。書斎もまた然り。読まず、書かず、時間のみ過ぎゆけば生が薄まる。
この繊細な力関係の間で机が窓側から部屋のど真ん中に移動したり、ベットが西向きになったり東向きになったりぶっ壊れたり、ホワイトボードが邪魔になって捨てようと思ったけどやっぱりやめたりと、数ヶ月ごとに家具同士、熾烈な縄張り争いを繰り広げる。
そんな日々の闘争を促す、ある訪問者の存在がある。私が自堕落になったり、よからぬ人々と付き合い始めたり、相性の悪い趣味を持ち始めたりするとき、まるでそれらを見定めたかのように、彼らは訪れる。仄暗い押入れの奥から、家具たちの暗がりの中から、あるいは豪放磊落にも、台所のざらついたステンレスの上に、あの黒光りした悪魔が出現するのである。
連続と停滞の中に麻痺した間抜け面で、長々とテレビを見ていたり、お腹が重くなってしょうがない資質まみれのスナックをほおばってうたた寝していたり、何日かぶりに部屋に帰ってきたり。
日々の連続。停滞し、行き所を失ったみずみずしい何かが、濁り、沈滞し、黄昏の中に消えゆく。私は疲れている。全てに飽き飽きしている。理性に重たい靄がのしかかる。
そんな横づらをひっぱたくように、冷たい緊張が全身を満たすのだ。ふっと視界のすみに、不気味な影が横切った時にはもう遅い。そうだ、遅過ぎるのだ。暗い予感の中に、あのGの文字が浮かぶ。
凍りついた体をゆっくりと傾けて、その予感の方へ目を傾けると、やはりいるのである。奴が。
時間が止まり、その衝撃に身を凍らした者はただ、虚空を見上げる他ない。その沈着な表情に全てが矛盾するような、まるで日常では発されることのない奇声が喉を震わす。鼓膜を通して鳴り響くその奇声に、改めて驚きと耐え難い自己嫌悪を感じたところで、その恐怖の存在とのファーストインパクトは遂げられた。もうよい。結局、やるしかないのだ。
そっと秘密のロッカーから毒薬を取り出し、逃げ惑う悪魔の一挙一動に怯え飛び跳ねつつ、奴が暗がりに逃げ込んだが最後。室内全体が煙くなるほど大量に毒の濃霧を噴射し、仰向けになってジタバタとあがく奴に1ミリでも憐れみを感じることはない。その黒い光沢を覆い尽くすほどの毒の厚塗りでオーバーキルである。
冬物の手袋を装着し、なんでもいいから棒を見つけ、その先にガムテープを筒状にはる。そして今なお弱々しくあがく黒い悪魔の感触を棒先に感じて慄然としながらも、その体を窓の外に投げ捨てるのだ。
一連の悪魔祓いが済んでいつも(もし途中で逃げられでもしたら最後、私は早急に引っ越さざるを得ない)、この疑問に出くわす。
かくも奴を恐れ、嫌悪させるものは何か。
昔からの家の習わしで、家中を這い回るクモは殺さない。だからか奴らが出現しても、不思議と全く動じない。むしろ我が領域に侵入を試みる別の化け物どもを退治してくれることだろう。
相当でかい南米クラスのクモにでも出くわさぬ限り、奴らは恐ろしくないのだ。それでは一体なぜ、同レベルにグロいはずのGのみがかくも深甚なる心的打撃を強いるのであろうか。
そんな疑問を残したまま、悪魔祓いの後はいつも、模様替えを行う。
部屋の隅々までが清潔に片付けられ、机やベット、冷蔵庫の位置が激変する。
幾年もの闘争を経て、再び新たにされた整った室内を眺め、お茶をすすっていたある日曜日の朝、東から新たにされた陽光が書斎に並ぶ愛しい本と文具たちを照らし、きらびやかな光沢で私を誘った。その時、私は気づいたのだ。この部屋、この空間は、私の脳内そのものなのだと。
Gへの極端な嫌悪も、それで説明がつくのだ。自己によって秩序立てられ、選択、選別された限定空間に、自己の意志と秩序に全く関係なく、自由に這い回る存在がある恐怖、そして不快感。そうか。これであったのだ。
現在住んでいる部屋は左右それぞれに均等な大きさの空間があり、その機能にも確固たる棲み分けが発生する。いずれかの極に理性が宿り、その反対の極には情動が渦巻く。時期によっていずれかの極にて安逸を貪り、その反対の極はただ埃をかぶっていることが多い。その変容はまるで活性の時を異にする我が右脳左脳のごとき克明な棲み分けに思える。
押入れもまた面白い。それは潜在意識の空間とでも言えようか。
そこでは不要になりながら捨てるに捨てられなかったもの、日常ではあまり機能しないが、たまに使われるものがぶち込まれている。この場所を乱雑に放置しておくと、大事なものはその混沌の中で姿をくらまし、部屋の中で不要になったものを詰め込みたくもスペースは足りなくなり、ある季節の変わり目の日、布団を出そうとしたときに雪崩となって我が身を襲う。
あるいは過去にしまわれた恥辱に満ちた手紙や写真が行き場を失って混沌の中に混じり合い、求めてもいないときに姿を表してきゃーとさせる。
あるいは呪わしきGが住み着き、繁殖せんと試みるのも押入れである。Nなどは問題外。
ホラー映画にしても恐怖の潜む場所は常に地下室か天井裏。要するに特大の押入れ空間と言えよう。そこに宿るであろう特大のGないしNは、ホラー映画の主題になって然るべき混沌の使いであろう。
そう、模様替えを繰り返した果てに目の前に広がる限定空間は、いつも私の価値観、無意識下の選択、快・不快の表出であるわけである。その空間は私の脳内の箱庭なのだ。
最近もまた、私は悪魔と一線を交え、激戦の末に勝利した。木造の壁に寒さの染み渡るのがどこか心細い、白い息の出る冬の日であった。
しかし私は悪魔が出て仕方なき生活を送っていたのだ。
幾多もの模様替えが、奴らに催されて行われたものであったとすれば、奴らは我が空間、我が家具たちの送りたもう何がしかの使いであって、悪魔と呼びすてられてこそ、その怨念も安まるところを知らず私を苛むであろう。
今回に限って私は手袋もせず棒も使わず、テイッシュ一枚、やつの体を包んで、トイレの水に流した。
この大都会の中に薄壁一枚を隔てて、その限定空間に不安な個を育むしかない我々は、このGとの邂逅、あるいは対話無くしては、ただその林立するビル群と住宅群の渦に、その日常からもたらされる絶えざるささやきと雑音に、ただ従い呑まれぬほかないのではないか。おおGよ。
私は巨大なホワイトボードがなるべく窓を隠さぬよう部屋の端っこに位置を変えた。めちゃくちゃ大きな押入れの扉を取っ払ってその空間にテレビをぶち込み、美しいシンメトリーを誇る映画鑑賞スペースを作り出した。
幾何学的な棚の一部を外してそこに冷蔵庫をぶち込み、周りには観葉植物やおしゃれアロマ、なんの役にも立たないモニュメントを飾り立てた。
玄関に入ってすぐ横の広い無駄なスペースに本棚を置いた。出かける時、帰ったときすぐに目に入るのは愛しい本たちだ。
そして書斎はベットのすぐ横。今や寝室は書斎なのだ。
またGが出るというなら私は戦おう。そのグロテスクな見てくれへの衝撃は半ば薄まり、身勝手な愛おしさすら覚えている今のことだ。嫌悪と恐怖を乗り越えて、手厚く葬ることも厭わぬ。
しかしGよ。再び新たにされたこの部屋は、私の心をくすぐる。薄い壁の内に人知れず新たにされたこの光景は、日常を超えてあらゆる憧れを誘う。このあどけない喜びに心躍る今だけは、どうか現れないでほしい。再び会うその日まで、Gよ、安らかに眠れ。
小説 『永い言い訳』 に触れて
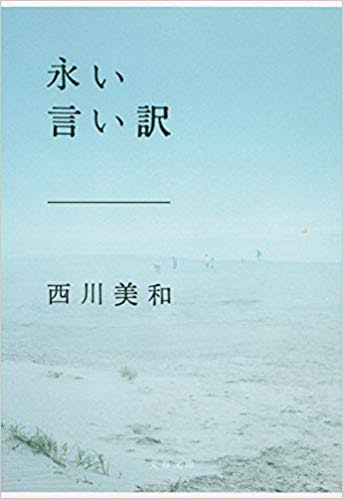
西川美和さんの作品を読んでいると、善い小説の真の効力を思い知らされる。
それは読者に「主観」を与えてくれることであると思う。
小説なのだから当たり前ではないか、と一瞬思いはする。
とは言っても、私たちの内面は日頃そこまで豊かに語らないし、仮に豊かな内面を秘めているにしても、日々の疲労、心労、自意識などによって麻痺し、硬化しているのではないだろうか。
小説の中で感受し、思考する内面の声を拾い、文字にすること、小説にすること、物語にすること。
それはゾンビのように脳内をフラフラとさまよい歩いている思索と感受に、美しい衣を着せて人間に戻そうとしている試みそのものである。
その人間が話し、考え、葛藤し、感動する姿を見て、読者もまた豊かな内面を微かにでも再生させることができるのだ。
善い作品は、健康な「主観」を与えてくれる、そう思うのだ。
モンテーニュ2
あらかじめ死を考えておくことは、自由を考えることである。
死を学んだ者は、奴隷であることを忘れた者である。
彼のこの言葉を聞いて、不思議と目の前に広がる光景が輝いては来ないだろうか。
しかし通常、なぜその光景は輝いていないのだろうか。
それは日常の心労が、広漠な糸を張り巡らせて我々を縛るからである。仕事、勉学、人間関係。休みない競争が、私たちを掴んで離さない。
忙しい日々の生活の中で死を考えることは思った以上に難しい。というより少し異常なこととも言えるだろう。
あまりにも大きな深淵たる「死」が想像し難ければ、小さな死を想像してみるのはどうだろうか。
たとえば日曜日である。
日曜の夕方、我々はなんとも言えぬ憂鬱にとらわれはしないだろうか。それは小さな死なのである。
金曜の夜に生を受け、無限に思える二日間に遊び、あるいは惰眠を貪る。そして我々は再び元の道に帰ってゆく。
そんな日曜の夕方、残された時間は妙に切ない輝きを宿していないだろうか。
あるいは卒業、別れ、旅立ちの時、そこで涙する人がいるのも、彼らがそこに死を垣間見るからではないだろうか
変わり栄えのない日常の繰り返しが儚い一瞬に思え、過ぎ去った日常の中に、美しい光があったことに気づく。
その時私たちは日々の連続と停滞を忘れ、その先に漂う死の香りをかすかに感じているとは言えないだろうか。
死のほのかな深淵より平凡な日々を覗き返した時、我々の生は思ったよりも短く、思ったよりも美しく、誇り高いものであることを知るのだ。
そんな光を前にして、広漠に張り巡らされた不安の糸はただ糸でしかなく、確かにここに呼吸し、世界を見、感じる生命の存在を思い出す。
その時人は、もはや日々の不安、日常の奴隷であることを忘れるのだ。
いずれにしても我々を迎い入れる死を前に、我々はその糸を引きちぎるも、紡ぎ合わせて遊ぶも自由なのである。
キャベツについて
最近たくさんキャベツを食べている。毎日ひたすら食べている。シャキシャキとあらゆる食事の味を引き立てるキャベツは、甘み、風味、食感、栄養、そのどれをとってもポテンシャルは無限である。
さらに言えばキャベツは消化にも優しい。消化によって体内の血液のほとんどを持ってかれると、人は眠気を覚える。視界はボヤけ、集中力もなくなる。気分と欲望の奴隷となるにはもってこい。意志薄弱の身体はあらゆる刺激に引きずられ、日常には間延びした影が差す。
生活をいかに己が理想に導きゆくか。栄養をいかに苦痛なく血肉に替えるか、それらを決定する重要な存在こそ、消化の質であると思うのだ。適量食べれば満腹、胃腸を滑るように流れて栄養となり、エネルギーとなるこのキャベツというやつは、人々の生活に革命をもたらしたのだ。
話は飛ぶが禁欲の修行僧を見て、その姿に人間離れした高尚を見るのだろうか?彼らが愚かな狂信者でなければ、彼らはただ自己選択によって己に最も快い生き様を選んだのである。彼らは消化に疲れ、消化に苦しんだ。そして極力消化を減らしつつ、この世界そのものを食すことを選んだ人々なのである。
話を戻そう。私がキャベツを食べるか、あるいはファ◯チキを食べるか判断するとき、そこには何の信仰もなく、道徳も理想もなく、ただ理性と計算に基づいた最大公約数の心地よさを求めてキャベツを選ぶのだ。ファ◯チキは大好きなのに、である。
しかし理性のなんと儚く気まぐれなことか。世間に溢れる多くのファ◯チキに、毎日を引きずり回されないこと、それはいかにして可能か。一日三食ファ◯チキ食べるのが常識の世界で、キャベツとかいう貧弱な味覚をあえて選んで、そのキャベツにこそ味の深みを見出し、秘められた栄養に健康を増進する日々は、いかにして訪れ得るか。
それを可能にするものは、今ではずいぶんと高飛車な言葉になってしまった「教養」というやつを他にしてありえないように思えるのだ。
教養のもたらす選択肢は、一見して非日常的、時に反社会的、稀に変態的ですらある。
しかしそれは日々新鮮な知恵と視野を与えてくれる。常識に閉じ込められた種々様々の可能性を垣間見せ、何ものも押し付けはしない。ファ◯チキのジューシーで脂ギッシュな味わいを超えた美味、珍味の存在を、ただそっと教えてるにとどまる。一人灯明の下で沈思する深夜、それは耳元に囁きかけるのだ。「キャベツ…」と。
それにキャベツは安い。ファ◯チキ一個の値段で優にひと玉、数日分のキャベツ生活を提供してくれる。キャベツ生活の至福を得るためには、富も地位も、健康すらも求められはしない。キャベツを得るためには、どんな隷従にも、どんな欺瞞にも屈する必要はない。
むしろそれらからの解放をこそ、キャベツは教えてくれるだろう。そう、キャベツは味もコスパも備えた、我々の最強の味方なのだ。
しかし真にキャベツを知る道は、長く険しい。ファ◯チキとキャベツの試行錯誤の日々は、時に不安であり、時には孤独ですらあるかもしれない。
時にファ◯チキファンを背にした孤独、孤立の日々に耐えるためにキャベツを神格化したりする。ファ◯チキファンを唾棄すべき俗人と見なして愛と友情に飢えたりもする。そんな内面の飢え、貧困を補うことほど、高くつくものはない。
どうかキャベツを神格化しないで欲しい。生でキャベツを食ってその味の深みを喧伝するような愚を犯さないでほしい。美味しいシーザーソースや粗挽き胡麻ソースをじゃんじゃんかけて味わってほしい。味覚の洪水のごときファ◯チキを細かく刻んでキャベツと一緒に炒めたり、ファ◯チキをキャベツとパンで包んでみるのも時には良い。時にファ◯チキに胃もたれしたその嘔気の苦しみが、キャベツへの道を開くであろう。
美味しくて体にいいからキャベツはキャベツなのである。より善き栄養として、より善き血肉となるからこそキャベツはキャベツなのである。
モンテーニュ1
自分の存在を正しく享受することを知ることは、ほとんど神に近い絶対の完成である。
我々は自分の境遇を享受することを知らないために、他人の境遇を求め、自分の内部の状態を知らないために、われわれの外へ出ようとする。
だが、竹馬に乗っても何にもならない。何故なら、たとえ竹馬に乗っても、なおかつ自分の足で進まねばならないし、世界でもっとも高い玉座に昇っても、やはり自分の尻の上に座っているからである。
もっとも美しい生活とは、私の考えるところでは、普通の、人間らしい模範にあった、秩序のある、しかし奇跡も異常もない生活である。
モンテーニュの言葉を聞いているといつも、自分を背伸びして見せることがバカらしく思えてくる。凡庸であることを恐ろしいとは思わなくなる。
「答えはあなた自身の内部にある」どこかで聞いたような言葉である。要はモンテーニュも、よくある自己啓発本に載っているような「自分自身賛歌」を書いていることに違いはないわけだ。
しかし彼は自分自身を決して高いところには置かない。人間誰もが持っているもっとも基本的なスペック、つまりは経験と感受そのものを、いや、そんな言葉すらもいらない。「生命」そのものを、まるで子供のように慈しんでいるのだ。
幼少の頃からラテン語をマスターし、書物と教養のお化けのような存在であったにも関わらず、彼はもっとも素朴に「生」そのものへの愛の賛歌を歌い続けている。
彼が「自分自身」について語るとき、そこには自我の臭みがない。彼の稀有な経験、そして類まれなき教養と才能は、「生」にまとわりつくあらゆる虚飾を退けることに費やされた。それは何と幸福なことだろう。
人間誰もが持っている「自分自身」を、血眼に装飾し、虚栄に浸ること。そんな竹馬も王座もいらぬと、彼は言う。奇跡も異常もいらないのだと言う。
そこにこそ自由があるのだと思う。生の喜びもまた。
ゴヤ 『聖イシードロの巡礼』

何の喜悦も感じられず、また暴動様の怒りもない。祭りの日の巡礼とならば、共通の目的がありそうなものなのに、それもない。
人間は無意味に口をぱくぱくやり、目の玉をぎょろつかせて荒野を目的なく彷徨する集団に過ぎない。
人生もまた生から死への無意味な巡礼であるか…
激動のスペインを生きた宮廷画家、ゴヤはある時期、「聾者の館」と呼ばれた邸宅に引きこもる。その場所で誰に公表するつもりもなく、直接邸宅の壁におどろおどろしい奇怪画を描き続けた。俗に「黒い絵」と呼ばれる作品群である。
我が子を喰らう父、棍棒で殴り合う男たち、魔女に連れ去られる人間、砂に飲まれゆく犬…。残酷で陰惨な作品の数々にも関わらず、この「黒い絵」は多くの人を魅了してきた。
そこには怖いもの見たさ、怪奇趣味などといったこととはまた別の、不思議な魅力があるのかもしれない。そこに描かれている魑魅魍魎たちは確かに、私たちの日常の中に存在し、時に対峙を迫る存在に思えるのだ。

暗さ、救いのなさ、残酷さ。かくまでも赤裸々に、なんの虚飾もなく壁に描きこまれた魑魅魍魎の世界。その生身の姿の放出を前にして、凄まじい生命力を与えられるとでも言えばいいのだろうか。
『聖イシードロの巡礼』もまた、我々の世界に確かに存在する光景なのだと思う。どこにその巡礼を見出すかはその人次第ではある。私個人にとっては、日常の至る所にこの巡礼をみる思いがする。
連綿と連なる人の列は、狂気と悲壮に満ちた相貌の人々を先頭に、怯えるように歩みを進める。堀田善衛の指摘する通り、それは人生そのもの、先頭の彼らは目前に迫る死を前に怯え、すくみあがっているように見える。

最前のギター弾きの顔つきの、なんと狂気に満ちて悲壮なことか。彼のかき鳴らす音色は、聾者のゴヤと同じく我々には聞こえない。
時代ごとに異なる音色が掻き鳴らされてきたことだろう。現代社会においても連綿と続くこの行進において、そこにはいかなる音色が掻き鳴らされていることか。
そしてまた、独り行進から離れ孤立して、画面の外を見つめる人間が右端に在る。彼が目にしている風景はいかなるものであろうか。
堀田善衛の指摘によると、彼の視線の先にはもう1つの黒い絵作品、『我が子を喰らうサルトゥヌス』像がそびえ立っていると言う。何とも救いのない話である。そこには何1つ安易なカタルシスがない。
しかしゴヤはこの黒い絵を邸宅の壁に描きつけ、その中に暮らした。見る人を凍りつかせるような狂気、陰惨さ、救いのなさに形を与え、その中に生きた。
魑魅魍魎は姿を与えられることで潜在の混沌であることを止め、過酷な現実を受け入れる、あるいはそれと対峙する覚悟へと姿を変える。
ゴヤ自身もまたこの巡礼から離れ、あるいは離され、その外側でこそ自由に世界を見る人であった。
その目に映る光景に画家の長年の経験と技術が結晶し、他者である我々の心をも動かす生命の強さ、尊さへと昇華されていく。
かの巡礼を観て、我々はいかなる覚悟、あるいは力を与えられるものであろうか。