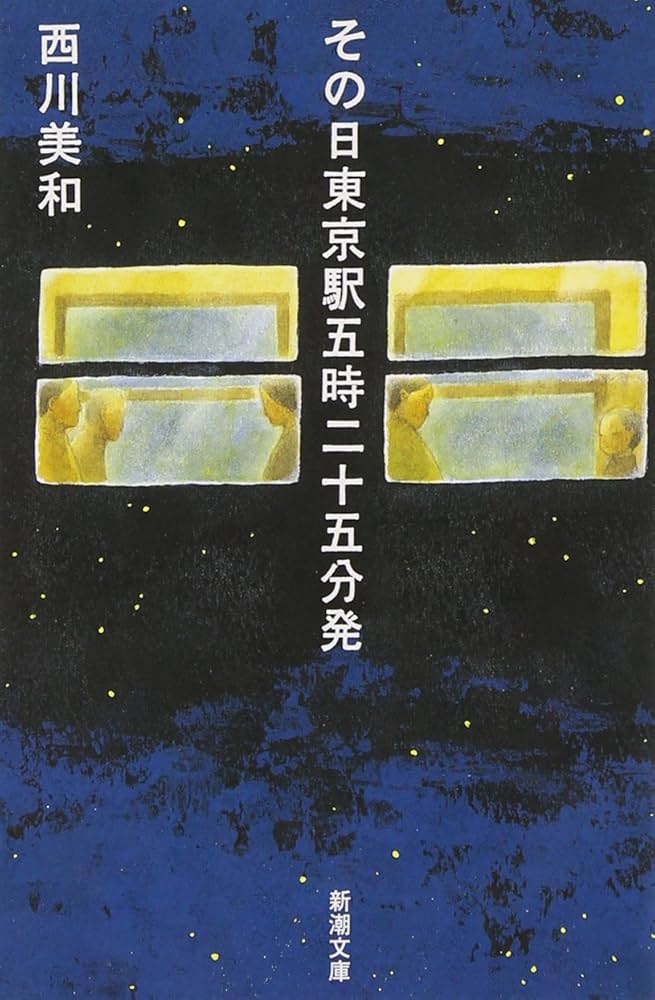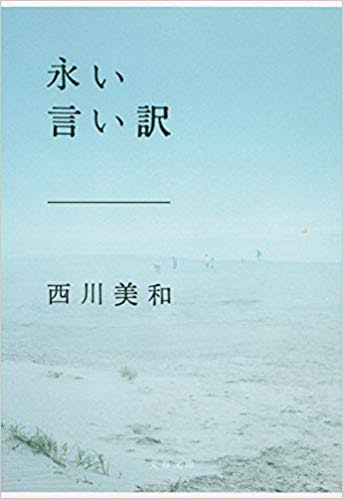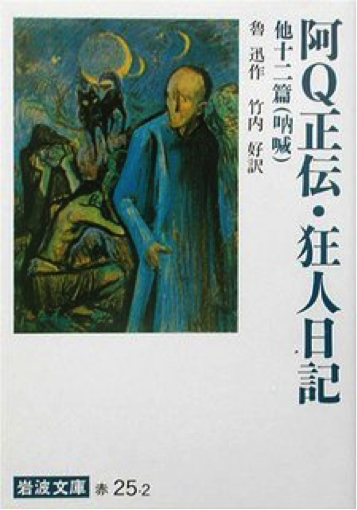マルメラードフという人間をご存知か?
『罪と罰』に登場する正真正銘のクズ人間である。
家の金を抜き去って妻子を飢えさせ、極貧に狂った妻が子供を虐待しているのを知りながらも、マルメラードフは酒に酔って寝ている。
その妻子の面倒を見ている心優しい十代の娘がいる。彼女は荒んだ継母の世話をし、泣きじゃくる継母の子供たちを食べさせるために体を売っている。
その娘の金すらも彼は無心するのだ。そして何に使うかといえば当然酒である。そしてマルメラードフは酔って寝ている。
マルメラードフは人間と呼ぶにも値しないクズ人間である。
ドストエフスキーはどうしてこうまでもクズな人間を人として描けるのだろうか。
彼の悲しみすらも失った放心、酩酊状態の深淵の淵に垣間見えるもの、人間であることの微かなる残渣のようなものをドストエフスキーは余すことなく語るのである。
家族への強い愛、微かなる学識と知性、そして強すぎるプライド。それらがありながらにして、マルメラードフは酔って寝ているのはなぜなのか。
彼、あるいはドストエフスキー作品にしばしば登場する、誇り高く、破滅性に満ちたクズ人間は何を体現しているのか。
それは多かれ少なかれ、現代を生きる我々そのものなのだと思う。
誤解なきように伝えたいのは、現実にマルメラードフ規模のクズ人間はそう多くはないと思う。
しかし何かを裏切り続けながらもがき苦しんでいる人間、仕事や生活のもたらす辛酸一滴一滴に、少しづつ溶かされてはついに狂ってしまった人間、狂いの中で己にとって最も大切なものを傷つけている人間、それは多かれ少なかれ、近現代を生きる我々そのものであると思われてならない。
言い方を変えれば、マルメラードフが踏みにじった家族、それは現実に近代化やロシアの帝国主義時代に苦しんだ一般庶民の姿であると同時に、己自身の中で蔑ろにされた「魂」の体現そのものであると思うのだ。
その「魂」を人間性、愛情、理性、教養、情緒と言い換えられもするだろうか。いや、それは人によって異なるものだろう。
己の中に何か美しいもの、崇高なもの、尊いものを抱えながらも、それを大事にすることができず、快楽や惰性、愚かさ、ひいては酩酊状態に引き落とされた日常にあって、絶えずそれらを裏切り続けなければならないクズ人間の悲しすぎる人間性。
著者、ドストエフスキーにとっても、歴史的大著の作家であり、あえてここで語り直す必要もないほどの偉大なる彼の才能を持ちながらにして、彼は常に酒や博打、あるいは行きすぎた思想的熱狂に身を持ち崩した。
そのあまりにも鋭利な感受性、あるいは病に疲れ、凄まじい自意識に悩まされながら消耗し、怠惰になってしまった彼自身の姿そのものが、マルメラードフなのではないか。
宗教的な生の指標や村社会的な集団性の中にあった人々が、突如それらを剥奪され、近代社会の中で「個人」として生きなければならなかった時代、その自由と混沌の中で育まれる光と闇。
彼の破滅的な、あるいは停滞的な生活で蔑ろにされ、内側でもがいている何か、それらは彼の作品の中で別の姿をとって化けて出るのである。
すなわち極貧の中で泣き叫ぶ子供や、怒り狂う妻、健気にそれを耐え忍び続け、赦し続ける聖者となって、彼を苛むのだ。
『カラマーゾフの兄弟』の第三部に、その傷つきやつれた魂たちへの想いを綴ったようにしか思われない「夢」の描写がある。それは「餓鬼(がきんこ)の夢」として描かれている。
その夢の中で彼は問う。
「教えてくれ、どうしてああやって、焼け出された母親たちが立っているのか、
どうしてみんな貧しいのか、
どうして餓鬼はあわれなのか、
どうして草原は空っぽなのか、
どうして女たちは抱き合って口づけしないのか、
どうして喜びの歌を歌わないのか、
どうしてああして、黒い不幸で、ああも黒くなっちまったのか、
どうして餓鬼に、乳を飲ませてやれないのか?」
ドストエフスキー著『カラマーゾフの兄弟』光文社新訳文庫 亀山郁夫訳
夢を見たドミトリー(カラマーゾフ家の長男)は破滅と絶望の淵へ爆走するまさに真っ只中に、子どもと母親がこれ以上泣かずに済むように、今すぐ何かしてあげたいと願うのだった。
混乱と絶望の中にあって、悲しみと狂気に満ちてはいたクズ人間たちの中にも、餓鬼(がきんこ)に乳を与え、喜びの歌を歌った人間、例えばそれを文として、物語として、芸術・思想として昇華させた人間、つまりはドストエフスキー本人のことを思うと、この近代の殺伐の中にも、数多くの奇跡が生まれていることを知るのである。ドストエフスキーという偉大なクズ人間もまた、多かれ少なかれ今を生きる我々そのものなのだ。