魯迅『狂人日記』と『阿Q正伝』
近代の悩める自我について
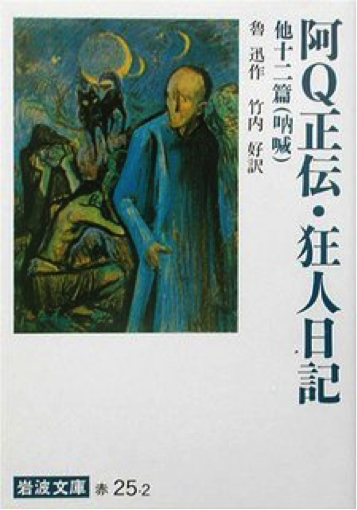
三十年ぶりに月光を眺めてから、突然に病理を深めていくある被害妄想狂の日記を描いた『狂人日記』で、終始表現される食人に対する嫌悪と恐怖。
近代に至り、生命が1つの権威や宗教と共に共同体の中に溶け込んでいた時代は去り、入り乱れる新旧の価値観の中で、各々が即席の自我の獲得を課されることとなった時代。
圧倒的な善として世界を闊歩した啓蒙思想の助けもあってか、従来の価値観は審問に伏され、悪徳として否定されることも珍しくないこの時代に、王政やキリスト教、そして儒教もまた、徹底的な打撃を受けた。
儒教的な価値観の弊害を食人として理解すればすっきりと読めるかもしれないこの作品は、しかし近代人が誰もが持つに至った不安定な自我への恐怖、つまり実存的な恐怖として読み解くことはできないか。
後天的に時代や環境から付与された思想なり価値観なり信仰なり、その総合の上に成り立つ我々の自我。これを育んだ近代化という時代的変遷のなかで、それを我が血肉のように重んじ、はたまた我が血肉のように傷つけられ、奪われ、食われはしまいか?己もまた他人の血肉を食った上で成りたった存在ではなかったか?このような、己の存在の所在に惑い、己の存在意義そのものに突き刺さる恐怖を、「食人」という野蛮な言葉で表現したのではないか。
また一方の『阿Q正伝』で描かれる阿Qの下劣で滑稽な生き様、それは即席で強い自我を背負わされた民衆に見る近代の殺伐と、その中でもがく人間たちの精神を描いたように思えてならない。
それは肥大化した自我やプライドに見合わぬ卑小な存在である一個人の、弱肉強食世界での悲しくもあり、可笑しくもある闘争である。
しかし民衆の不安定な自我の滑稽さ、あるいは恐怖を描きつつ、生命そのものに本来あるべき、畏敬に価する何かを描くこと、そしてそのような生命が時代に翻弄され、無残に散っていくことに対する怒りを表現することも魯迅は忘れてはいないように思われる。
それは阿Qが処刑される寸前に突然鋭敏に知覚される本質的な恐怖と、まさしく奪われようとする生命の、あまりにも生々しい呻きの言葉である。
最後の最後まで下劣で、間抜けであった阿Qの生命は、「にぶくて鋭い、彼のいったことをすぐに咀嚼しただけでなく、彼の肉体以外のものまでも咀嚼しようと、いつまでも彼のあとにくっついてくる」民衆の残酷な視線を前に自我を剥ぎ取られ、叫んだのだ。「助けてくれ、…」と。
その瞬間こそ、彼はその場に居あわせたあらゆる人々の中で、誰よりも真に人間ではなかったか。
狂人日記での食人への恐怖よろしく、霊魂までもが咀嚼される恐怖に見舞われた阿Q。その死には何の栄誉も、意義もなく、人々の好奇心をすら満足させることなく、惨めに散っていった。
時代を問わず、常にどこかで、日々新たに発され続ける彼の呻きの言葉は、儚い自我の強化に執心する現代人に鋭く突き刺さる。